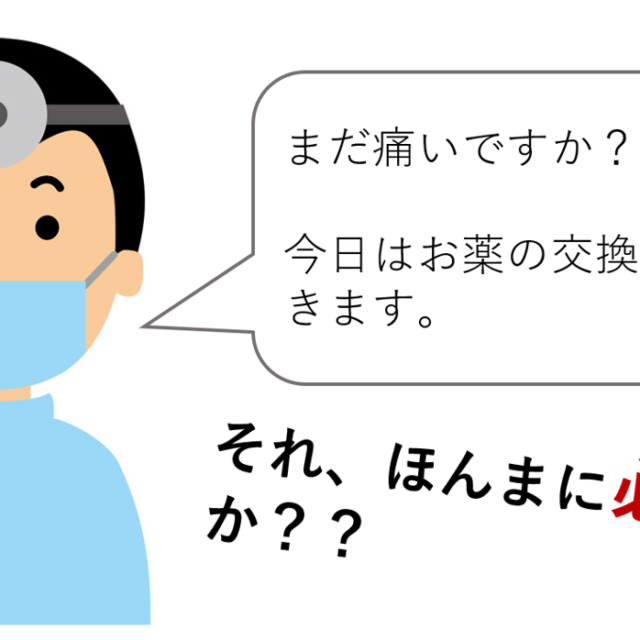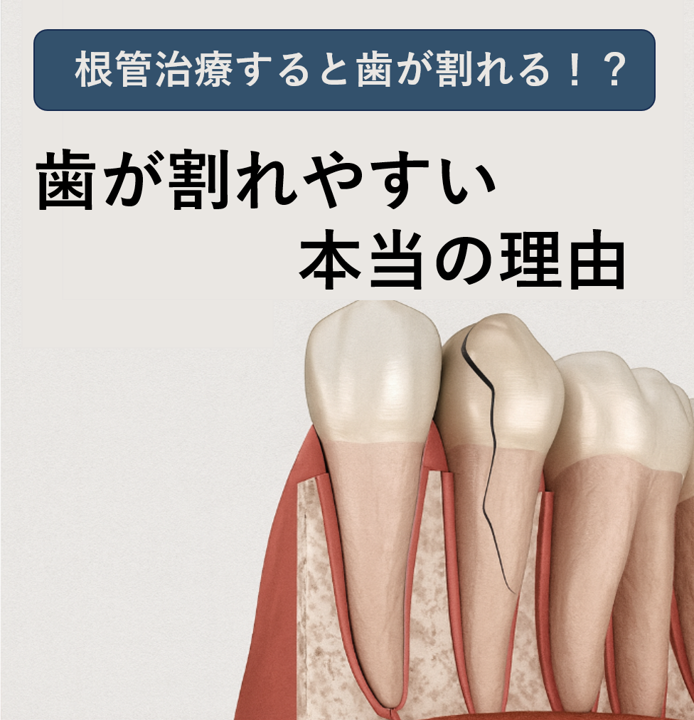🗓️ 最終更新日:
歯医者で塗られるフッ素は体に悪い?フッ素の効果と中毒性について
「むし歯になりにくくなるように歯にフッ素を塗っておきます」
「虫歯予防のためにフッ素入りの歯磨き粉を使ってくださいね」
歯科医院で歯のお掃除やメインテナンスを行った際に言われた方は多いと思います。
その一方、〖歯医者 フッ素〗とネットで調べると、“毒性・危険”や“事故”についてのサイトが多く出てくるため、フッ素を使用して本当に大丈夫なのかと不安になるのではないでしょうか。
本記事では、歯科医院で使用されるフッ素の効果や中毒のリスク、使用するポイントについて解説します。
そもそも“フッ素”とは何か
歯医者やテレビCMでは“フッ素”と呼ばれるのが一般的ですが、本来フッ素とは原子名であると定義されており、正式には“フッ化物(fluoride)”といいます。フッ化物の中でも、虫歯予防のために歯科医院で用いられるものはフッ化ナトリウム(NaF)やモノフルオロリン酸ナトリウム(MFP)と呼ばれるものになります。
なお、1982年にフッ化水素酸を誤って女児の口腔内に塗布され死亡事故につながった痛ましい事件があり(八王子市歯科医師フッ化水素酸誤塗布事故)、それによりフッ素が危険という認識をお持ちの方がおられますが、フッ化水素酸は人体に対して有害な薬品あり、お口の中に塗布することは絶対にありませんのでご安心ください。(そもそも通常の歯科医院には、フッ化水素酸が置いてあることはありません)。
フッ素の効果
フッ素には主に3つの特徴があり、これらの効果によって虫歯になりにくくすることができます。
再石灰化の促進
通常、歯の表面は中性に保たれていますが、食事をすると虫歯菌が食べ物の糖質を分解して酸を生成します。この酸により歯の表面のカルシウムやリン酸が溶け出してしまう現象を「脱灰」といい、溶けだしたカルシウムやリン酸が唾液の働きにより再び歯の表面に取り込まれる現象を「再石灰化」と言います。歯の表面は、常にこの脱灰と再石灰化を繰り返しており、脱灰のスピードが再石灰化のスピードを上回ると虫歯になってしまいます。
フッ素には、この再石灰化を促進し、歯にとって大事な成分であるカルシウムとリン酸
が歯に取り込まれやすくする働きがあるため、虫歯になりにくくなります。
歯の質を強化して、酸で溶けにくい歯に
歯の表面のエナメル質はハイドロキシアパタイトという成分でできていますが、フッ素が歯に取り込まれることにより、エナメル質の一部がフルオロアパタイト(FAP)やフッ化ハイドロキシアパタイト(FHAP)とう溶解性の低い結晶になるため、虫歯菌の出す酸に対して溶けにくくなります。
虫歯菌の活動を抑制
フッ素がプラーク(細菌の塊)に取り込まれると、むし歯菌の活動を抑制し、酸の生成を阻害するため虫歯になりにくくなります。
フッ化物の摂取方法
全身的な摂取
フッ化物が多く含まれた飲み物や食べ物を摂取することにより、消化管からフッ化物が吸収され、形成される歯のエナメル質にフッ化物が多く取り込まれるため、むし歯に対する抵抗性の高い歯が形成されます。
代表的なものとしては水道水中にフッ化物入れる水道水フッ化物濃度調整(日本では行われていません)や、フッ化物添加食塩、フッ化物添加ミルクなどがあります。
局所的な摂取
歯の表面に直接フッ化物を作用させる方法であり、日本で主に行われているのはこちらの局所応用です。
フッ化物歯面塗布
濃度の高いフッ化物を年に数回、歯科医院で歯に塗ることによって歯の質を強化させる方法です。歯磨き粉で認められているフッ化物の約9倍の濃度のフッ化物を使用することができるため、高い虫歯予防効果があります。
フッ化物配合の歯磨き粉
フッ化物が含まれている歯磨き粉を使用して歯を磨くことにより、歯の表面にフッ化物を取り込みます。どの年齢層でも手軽に実践できる方法であり、現在販売されている歯磨き粉の約9割にフッ化物が配合されています。
フッ化物の濃度は、6歳以上では1500ppmまで認められていることから、虫歯予防を目的として歯磨き粉を選ぶ際はなるべく高濃度のフッ化物が配合されている歯磨き粉(“高濃度フッ素配合”や“1450ppm”と書かれています)を選ぶことを推奨します。
フッ化物洗口
フッ化物洗口は、比較的低濃度のフッ化物配合のうがい薬を使用してうがいをすることによって、萌出後の歯に直接フッ化物を作用させる方法です。
うがいをする頻度には毎日法と週1回法があり、毎日法はフッ化物の濃度が225~250ppmと比較的低濃度のものを、週1回法はフッ化物の濃度が900ppmのうがい薬を使用します。
フッ化物は危険?中毒や副作用のリスクについて
虫歯予防に大きな効果があるフッ化物ですが、過剰に摂取してしまうと有害作用(中毒)を生じることがあります。
慢性中毒
長年にわたる飲料水やフッ素入りタブレットによりフッ化物を過剰摂取すると、歯の色が斑になる斑状歯や、骨の形成に影響が出てしまう病気である骨硬化症を発症することがあります。これらの症状は必ず起こるわけではありませんが、斑状歯は適量の2~3倍、骨硬化症は10倍以上のフッ化物を摂取した場合に起こる可能性があると言われています。
急性中毒
急性中毒は一度に多量のフッ化物を摂取したときに生じるもので、吐き気や嘔吐などの症状が認められます。
急性中毒を引き起こすフッ化物量は体重1㎏あたり2㎎とされており、体重50㎏の人であれば100㎎となります。100㎎のフッ化物がどの程度かというと、最高濃度のフッ素(1450ppm)が入っている歯磨き粉で計算すると約70gの歯磨き粉に相当します。旅行用歯磨きキットに入っている小さめの歯磨き粉が約20~30gですから、通常の試用では中毒の心配は全くないことが分かります。
ただし体重の軽い子供が、大人用の高濃度フッ素配合の歯磨き粉をチュウチュウ吸った場合には急性中毒になる可能性があります。もし誤ってフッ化物を過量に摂取した場合は,カルシウムを多く含む牛乳あるいはアイスクリームなどを経口投与することで、 フッ化物が吸収されにくくなります。
まとめ:一人ひとりのむし歯リスクに合わせたフッ化物の使用がおすすめ!
本日はフッ素(フッ化物)の効果と問題点について解説しました。
フッ化物には、一般的に使用される量を超えて多量に摂取すれば中毒を起こすリスクはありますが、そのリスクをはるかに上回るメリット(高い虫歯予防効果)が認められています。
これまでに一度も虫歯になったことのない虫歯リスクの低い人は使用しなくても良いかもしれませんが、“子供のころからよく虫歯になる方”や“数年以内に虫歯治療を受けたことがある方”、“甘い食べ物や飲み物が好きな方”などのむし歯リスクの高い方は積極的にフッ化物を使用されることをお勧めします。
今回も最後までお読みいただき誠にありがとうございました。
本記事は、奈良県大和高田市にある歯医者(歯科医院)、斉藤歯科クリニックの齊藤伸和(日本臨床歯周病学会認定医・日本歯内療法学会会員)が監修・執筆しています。何か不明な点がありましたら、無料相談も受け付けておりますので、是非お気軽にご相談ください。
斉藤歯科クリニックの虫歯治療に関しては☟